受験英語の参考書には多くの名著がありますが、その中でもひときわ伝説的な存在として語り継がれているのが、旺文社から刊行されていた『試験にでる英単語』です。
 英語ツウ
英語ツウ通称「でる単」と呼ばれ、1960年代から1980年代にかけての受験生にとっての“バイブル”的な存在だったよ。
「なぜこの単語帳がそれほどまでに支持されたのか?」「どのような特徴があったのか?」「現代の単語帳と何が違うのか?」といった点を深掘りし、かつての受験界のスタンダードがどのようなものであったかを見ていきましょう。



関東では『でる単』と呼ばれることが多く、関西では『シケ単』と呼ばれることが多いみたいね。
『試験に出る英単語』の基本情報
- 正式名称:試験に出る英単語
- 出版社:青春出版社
- 初版刊行年:1967年
- 著者:森一郎
- 通称:「でる単」
- 主な対象:大学入試受験生(特に国公立・難関私大志望者)
当時の英語教育は、文法・読解・単語の暗記が中心で、「とにかく覚えろ」という時代でした。そんな中で『試験に出る英単語』は「出る単語だけ覚えればいい」という実利的なメッセージを前面に打ち出し、爆発的に売れたのです。



今では考えられないことだけど、『赤尾の豆単』の語数は、7,768語と『でる単』の約1,500語と比べて膨大だよね。



当時の高校生は負担感大きかったはずね。効率を無視して、根性論で単語を覚えていたのね。



『赤尾の豆単』は完全なABC順で語彙が並んでいたため、受験生にとって重要語や出題頻度が不明確だったけど、『でる単』では「試験に出る順」=頻度主義に基づいて構成されてたから、重要語が一目でわかるようになったのが画期的だったんだろうね。



『でる単』は、効率的にスコアアップを狙いたい受験生に刺さったのね。
『試験に出る英単語』の特徴
『でる単』の特徴を説明します。
出題頻度に基づく単語のランク分け
この単語帳の最大の魅力は、単語の「頻出度」を3つのランクに分類していた点です。
- 頻出度A:絶対に覚えるべき最重要単語
- 頻出度B:できれば押さえておきたい重要単語
- 頻出度C:余裕があれば覚えるべき補助的単語
この分類によって、受験生は自分の学力や残り時間に応じて「Aランクだけまず完璧にする」「Bランクまで覚える」など戦略的な学習が可能になりました。
これは現代の『ターゲット1900』や『システム英単語』の基礎になったとも言える革新的な方法です。
以前の受験用英単語集(旺文社の『豆単』など)は、『ソーンダイク式英単語統計表』に基づいて、米国の新聞(英語)などで使われる頻度の高い単語が掲載されていた[5]。
また、『豆単』がそうであったように、収録語はアルファベット順で掲載されることが常であった[5]。
しかし、大学受験に求められる語彙と日常生活で求められる語彙には隔たりがあり、また、学習効率からすればアルファベット順ではなく出題頻度順(ないしは受験における重要度の順)に掲載するほうが望ましい[5]。
それらの点をふまえ、過去の試験問題を徹底調査し、同書によれば「最も重要な単語から順番に配列」して出版されたのが本書であった[5]。
引用元:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A9%A6%E9%A8%93%E3%81%AB%E3%81%A7%E3%82%8B%E8%8B%B1%E5%8D%98%E8%AA%9E
赤シート学習に対応
『でる単』は赤シートを使って、訳語や例文を隠しながら学べるようなレイアウトになっていました。これにより、反復練習がしやすく、スキマ時間でも効率的に学習できる仕組みが整っていたのです。
この方式はのちの多くの英語参考書に受け継がれ、「赤シート対応」は単語帳の定番スタイルとなりました。
なぜ『試験に出る英単語』は伝説になったのか?
実際に「当たった」単語が多かった
当時の大学入試は、現在ほど語彙が多様化しておらず、頻出単語がかなり固定化していました。
『でる単』に載っている単語を覚えるだけで、実際の入試の英文が読めてしまうことも珍しくなかったのです。
予備校や高校での推奨
多くの進学校や予備校でも『でる単』が推薦図書として使われ、教師たちも授業で使っていました。
「この単語、でる単のAランクに載ってるよ」といった言葉が飛び交うほど、共通言語となっていたのです。
シンプルさと信頼性
収録語数は約1000語と、現代の単語帳に比べれば少なめですが、それだけに「無駄がない」「本当に必要なものだけ」という安心感がありました。
『でる単』の著者・森一郎氏とは?
著者の森一郎(もり いちろう)氏は、東京都立日比谷高校で英語科の教員として1955年から1968年まで務めた教育者で、1967年には大学入試向けの革新的な英単語集『試験に出る英単語』(通称「でる単」または「しけ単」)を出版し、受験英語界に大きな影響を与えました。
日比谷高校では自発性を重視し、リーダーによる高度なリーディング授業(例:オーウェル、モームなど文学作品を英語で)を展開する中、森氏は「プラグマティックに受験英語に特化」した教授法を導入。校内では異色と見られることもありましたが、生徒には好評だったと伝えられています
時代の変化と『でる単』の役割の終焉
1990年代に入り、大学入試の出題傾向はより多様化し、TOEICやTOEFLなどのグローバルテストの影響を受けて、実用英語が重視されるようになりました。それに伴い、単語帳も長文化・コロケーション重視・例文読解型など多様な方向へと変化していきます。
その結果、『でる単』のような「単語→意味」といった直線的な構成は時代に合わなくなり、自然と書店から姿を消していきました。



1990年頃には、『試験に出る英単語』は、単語集No1の地位を『ターゲット1900』に奪われたと言えるね。



abc順の単語帳が主流だった当時のNO1単語集が『赤尾の豆単』だったみたい。その『赤尾の豆単』を時代遅れに追いやった『試験に出る英単語』も『ターゲット1900』によって主役の座を奪われたと父が言っていたわ。



『赤尾の豆単』って古いね(笑)
『赤尾の豆単』世代の人は「abandon」という単語に格別の思いがあるみたいだね。



えっ、なんでかしら。「abandon」=「放棄する」だから挫折した人の恨み言かしら?



いや。違うよ。
abc順の単語集だけに『赤尾の豆単』の冒頭に出てくる単語が「abandon」だったんだ。だから、英語をあまり勉強しなかった受験生が、一般的には難しいはずの「abandon」だけは覚えたと自虐的に言うネタみたいな感じだね。


『でる単』が現代に与えた影響
『でる単』以前の一時代を築いた『赤尾の豆単』は、試験に出る英単語を選ぶという点では『でる単』と同じコンセプトを持つと思われるかもしれません。
しかし、『赤尾の豆単』は、試験に出る英単語7,768語を収録という網羅性の高さで人気を博しました。
もちろん、試験に頻出の英単語の中に、a、the、I、youという超基礎単語も含まれていました。
そんな非効率性を排除したのが、『試験に出る英単語』でした。
『試験に出る英単語』では、収録語数が約1,500(初期)と『赤尾の豆単』の5分の1以下に抑えられているのです。
『赤尾の豆単』は、努力と根性の象徴的単語帳でしたが、
『試験に出る英単語』は、合理的で楽しく覚えられる新時代の単語帳として登場し、
時代の変化とともに、主役の座を奪っていったのです。
現代の人気単語帳の多くが、『でる単』の手法を進化させているといっても過言ではありません。
- 『ターゲット1900』:重要語をランク別に配置し、効率的な学習が可能に。
- 『速読英単語』:文脈で単語を覚えるが、見出し語の取捨選択に『でる単』の発想が生きている。
- 『システム英単語』:重要語をまとめ、ミニマルに学習するスタイルが共通。
今なお「でる単信仰」ともいえる精神は、多くの単語帳に受け継がれているのです。
おわりに|『でる単』が教えてくれたこと
『試験に出る英単語』は、時代のニーズに応じて生まれ、長く受験生に寄り添ってきた名著です。その構成の合理性、信頼性、学習効果の高さは、令和の今でも学ぶべき点が多いといえます。
情報があふれる現代だからこそ、かつての「本当に大切なことを、確実に覚える」という学習姿勢が、あらためて見直されるべきかもしれません。
「でる単」はもう手に入らないかもしれませんが、その精神は今の学びにもきっと活きてくるはずです。
時代の変化とともに英語教育の傾向も多様化し、『でる単』のような「単語の羅列」スタイルの本は次第に姿を消していきましたが、
その影響力は非常に大きく、今日の「ターゲット1900」「システム英単語」などにも思想的な系譜が引き継がれています。まさに「伝説の英単語集」として、今でも語り継がれる一冊です。
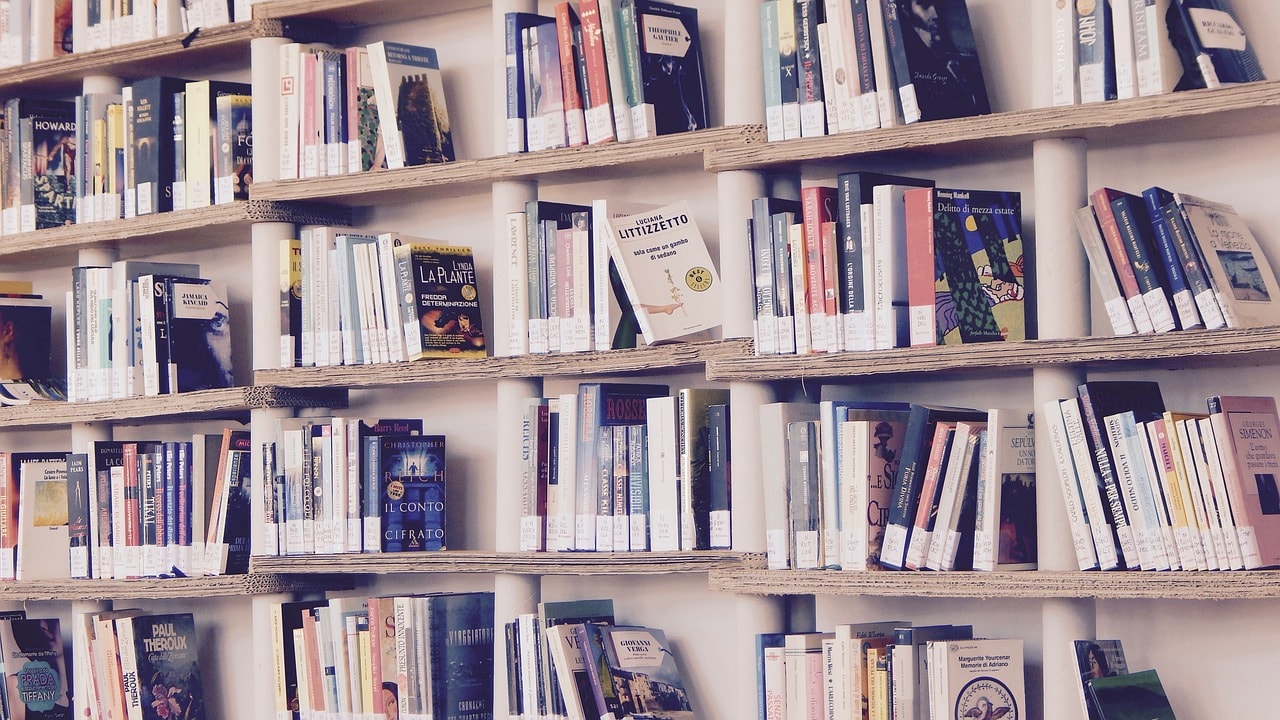




コメント