世界史の学習において最も人気が高いジャンルのひとつが「実況中継系」の世界史の通史を学べる参考書です。
講義を“読む”スタイルで、先生が目の前で話しているような感覚で理解が進むため、「世界史が苦手 → 一気に好きになる」という受験生も少なくありません。
とはいえ、このタイプの本は“読みやすいがゆえの落とし穴”も存在します。ここでは、実況中継系を使うメリット・デメリット、そして合格につながる使いこなし方を丁寧にまとめます。
実況中継系とは、世界史の出来事や人物を、単なる暗記事項としてではなく、物語として理解できるように語るタイプの通史参考書です。
まるで教室で先生の授業を受けているかのような臨場感があり、歴史の流れを「説明されながら追っていく」感覚で学べるのが大きな特徴です。
講義口調・会話調を基本とし、「なぜこの戦争は起きたのか」「この人物はどんな立場で行動したのか」といった背景や因果関係を丁寧に解きほぐしてくれるため、出来事同士のつながりが自然と頭に入ります。
さらに、図解・コラム・エピソードなども豊富に盛り込まれており、単調になりがちな通史を“読み物として楽しめる”構成になっています。
そのため、世界史に苦手意識を持つ人でも取り組みやすく、「暗記の前にまず全体像をつかみたい」「流れで理解したい」という受験生にとって、学習の入口として非常に相性の良いジャンルだと言えるでしょう。
おすすめの世界史通史の参考書5選
実況中継系の世界史通史は、「流れで理解したい」「暗記の前に全体像をつかみたい」という受験生にとって、最初の一冊として非常に心強い存在です。
講義をそのまま読んでいるような語り口で、出来事の背景や因果関係が自然につながり、世界史が“物語”として頭に入ってきます。
ここでは、数ある実況中継系参考書の中から、読みやすさ・理解のしやすさ・入試へのつながりという観点で厳選したおすすめ5冊を紹介します。
それぞれの特徴を比較しながら、自分に合った一冊を見つけてください。
世界史探究授業の実況中継
やはり実況中継と言えば、このシリーズ!
人気講師による“授業を紙面で再現”した講義形式の通史教材です。話し言葉で書かれており、歴史の「流れ」や「なぜ起こったか」という因果関係が自然と把握できます。別冊プリントや音声ダウンロードも付属しており、読むだけでなく聴く・整理する形式で学習できるのも魅力です。流れを理解したうえで暗記に入る入口として非常に優れています。
荒巻の新世界史の見取り図
世界史の膨大な流れと因果関係を、図解で「一目でつながる理解」に変えてくれる決定版
豊富な図や地図を用いて世界史の「大きな流れ」と「因果関係」を視覚的に整理できる点が大きな魅力です。 特に、細かい年代や用語に深く立ち入らず、まずは“物語としての世界史”を掴む構成になっており、理解を重視する受験生にうってつけです。
大学入試 ストーリーでわかる世界史探究
難関大学に求められる細かい知識も学べる
通史を「出来事の因果関係とストーリー」として語る構成が最大の魅力です。単なる年号・語句の羅列ではなく、各時代・地域がどうつながり、なぜ動いたのかが自然に理解できます。
山川世界史ナビ
改訂版 大学入試 茂木誠の 世界史探究が面白いほどわかる本
歴史の流れをストーリーで鮮やかに描き、世界史が「暗記」ではなく「理解」でスラスラ頭に入る決定版
人気講師・茂木誠先生の講義を“そのまま紙面化”したような構成で、ストーリー仕立てに歴史の流れや因果関係が語られています。ビジュアルや図版も豊富で、読むだけで「世界史がつながって見える」ようになるため、通史理解を軸にした学び直しに最適です。
実況中継系を選ぶメリット
① とにかく読みやすく、理解が圧倒的に進む
教科書のような硬い文体ではなく、語りかけるような文章のため、世界史が苦手な人でもスムーズに読み進められます。
また「背景 → 原因 → 結果」という流れが自然に追えるので、ストーリー理解が深まるのが最大の強みです。
② 世界史を“好き”にさせてくれる
実況中継系の魅力は、事実だけでなく背後にある人間ドラマや社会の動きまで描いてくれる点です。
「世界史っておもしろい」「もっと知りたい」と感じさせてくれるため、学習のモチベーションが続きます。
③ 流れの把握に最適
共通テスト・二次試験どちらでも重要な大きな流れの理解が圧倒的にやりやすいのが特徴です。
特に「古代→中世→近世→近代→現代」のつながりや、地域ごとの関係性がイメージでつかめます。
④ 教科書の“補助線”として非常に優秀
学校の授業や教科書では省略される部分もカバーし、“なぜその出来事が起きたのか”を明確に示してくれるため、後の暗記がスムーズになります。
実況中継系のデメリット(弱点)
① 読みやすいがゆえに、記憶が残りにくい
最大の注意点はここです。
実況中継系は物語として理解できる半面、語り口調の文章はそのまま暗記には直結しません。
そのため、
- 読んで満足してしまう
- 読書感覚で1周しただけで「わかったつもり」になる
- 本番で必要な用語レベルに落とし込めていない
という状態に陥る受験生が非常に多いです。
② 必要な“用語の粒度”が弱いことも
教科書・用語集よりも説明がなめらかなので、試験で問われる細かな用語・語句が薄いことがあるのもデメリットです。
特に早慶・難関国公立を志望するなら、どこかで問題集や一問一答で知識を補う必要があります。
③ 分量が多く、最後まで読み切れない人も
通史書はどうしても冊数が多くなり、実況中継系も例外ではありません。読みやすいとはいえ、途中で挫折する受験生も一定数います。
実況中継系を効果的に使う学習法
① 通史の導入として「最初の1周」は流れをつかむ
まずは“読むだけ”でOKです。
ここではストーリーの理解に集中し、細かい暗記はしません。ただし以下は軽く押さえておくとよいです:
- 大まかな時代の順番
- 重要人物と、どの時期に活躍したか
- 各文明・各地域の大まかな特徴
理解を優先し、止まらずサクッと1周してください。
② 2周目以降は「章ごとに暗記ターン」を作る
実況中継系の最大の弱点は読みやすさゆえの“暗記不足”。
2周目からは、以下のように“暗記モード”への切り替えが必須です。
- 章を読み終えたら
→ 一問一答 or 教科書 or 学校プリントで該当範囲を確認 - 重要語句にマーカーを入れる
- 暗記カードやチェックリストを作る
「読む → 問題で確認 → 覚え直す」という3ステップで定着率が大幅に上がります。
③ 必ず問題集で“出題のされ方”を確認する
実況中継系で世界史が好きになっても、試験では説明ではなく用語・因果関係そのものが問われるため、問題集は必須です。
例えば、
- 「なぜ〜か?」の論述的思考
- 正誤問題の細かい知識
- 図版問題や史料問題
など、実際の入試形式に触れて初めて「理解したつもりだったポイント」が洗い出されます。
これは非常に重要で、読んで満足している受験生ほど、問題に触れた瞬間に“自分が理解していなかった”事実に気づくことになります。
関連記事
世界史問題集おすすめ5選|効率的な勉強法と得点力アップの秘訣
世界史のおすすめ一問一答5選|最短最速で得点力を高める活用法
④ テーマ別に複数回読み返す
実況中継系はテーマ読みにも向いています。
- イスラーム史だけ読み返す
- 中世ヨーロッパだけ読み返す
- 日本史でいうと幕末だけ読み返す感覚
こうすると理解が立体的に深まり、共通テストのような横断型問題にも強くなります。
読みやすさの“罠”に注意(最重要)
実況中継系で最も多い失敗は、「読み物として楽しんでしまい、暗記を後回しにする」ことです。
以下は典型的な悪い例です:
- 「読むだけで分かった気になる」
- 「ストーリーは覚えているけど、用語が抜けている」
- 「一問一答を後でまとめてやろうと思い、結局やらない」
- 「実況中継系を5周したのに模試で点が取れない」
特に最後のケースは本当に多いです。
世界史の入試では、暗記事項の正確さが得点に直結します。
どれだけ理解していても、
- 年号
- 用語
- 正誤問題の細かい知識
- 地域史の特殊事項
が抜けていると点は伸びません。
実況中継系は“入口”として最高ですが、“出口(入試本番)対策”としては必ず問題集や一問一答と併用してください。
まとめ:実況中継系は「世界史を好きにしてくれる最高の入口」。ただし読みっぱなし禁止。
実況中継系は、世界史の通史理解の入り口としては最強クラス。
理解・流れ・興味喚起という面では、これほど優れた参考書群はほかにありません。
しかし、
「読むだけで覚えたつもりになる」という最大の落とし穴があるため、
- 2周目からは暗記に切り替える
- 問題集で出題形式を必ず確認する
- 用語の精度は一問一答で補強する
という“合わせ技”を必ず取り入れてください。









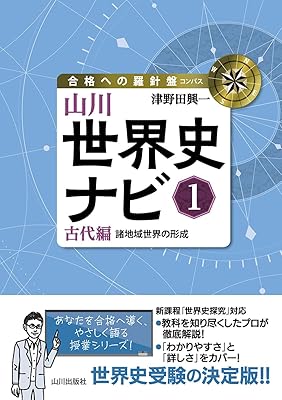
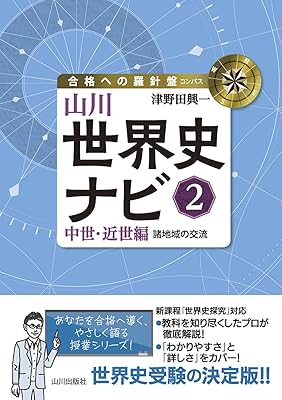
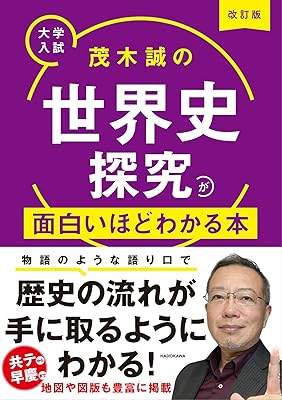

コメント